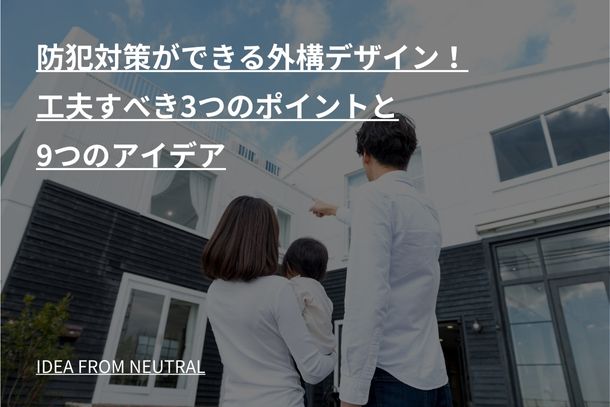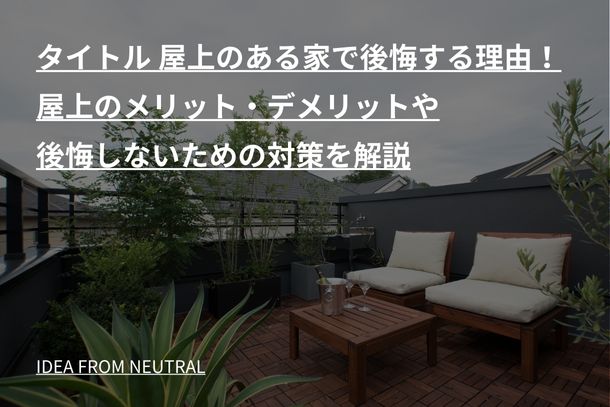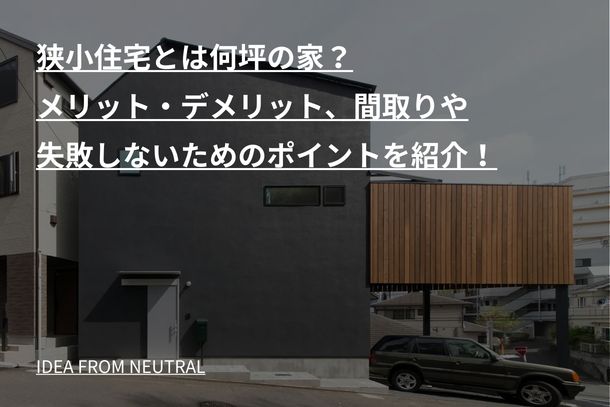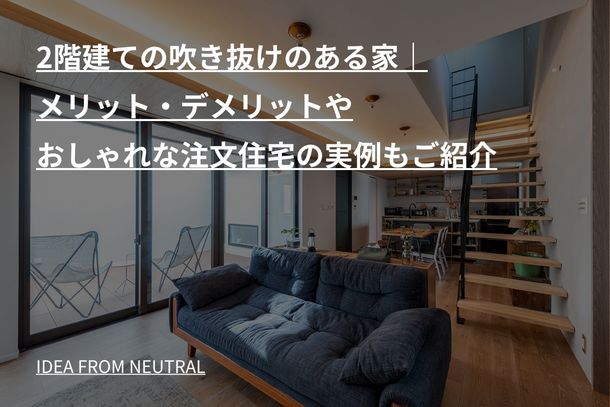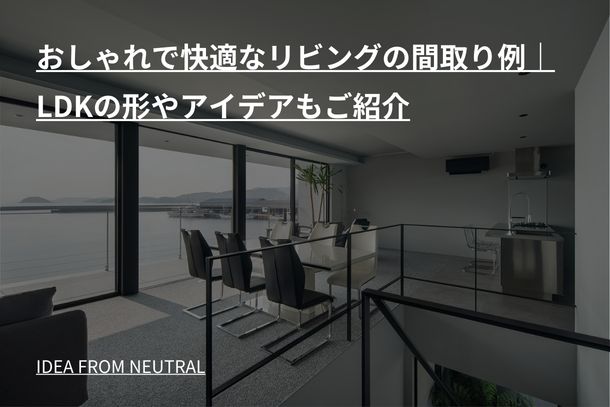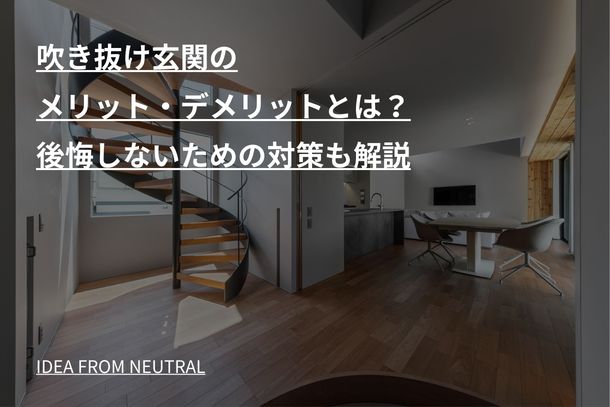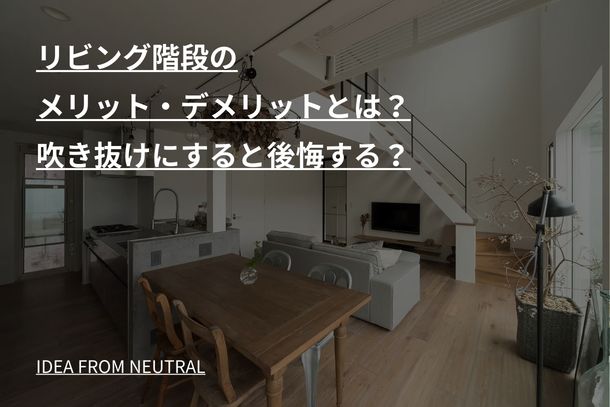CASE | 495 舞台の家
なるべく相場よりも安い価格で、賢く家づくりをしたいものですよね。そのためには、注文住宅を購入するための全体予算を知り、どんな費用がかかり、どんな要素が住宅取得金額に影響するのかを把握する必要があります。
住む地域によって土地や建築費の相場が違いますし、建てる敷地面積や住宅構造などによっても費用や価格は変わってきます。それぞれの要素をきちんと見極めることが、賢く住宅購入するコツです。
この記事では、「注文住宅の相場」「建築費別の建築実例」「資金計画の立て方」「費用・予算の節約方法」を解説していきます。また、価格帯別の建築実例もご紹介しておりますので、ぜひご参照ください。
無料住宅作品集の取り寄せ
建築費ごとの実例を含む、約40の実例写真・間取り・価格をご紹介。資料請求いただいた皆様に、無料でお届けします。
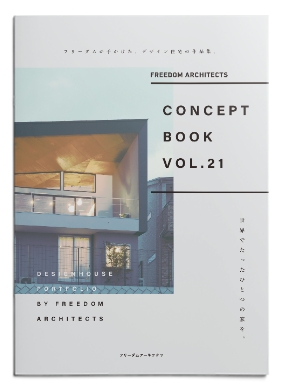
住宅作品集を取り寄せる
注文住宅にかかる費用の内訳
注文住宅を建てるときの費用内訳は、「土地代」「建築費」「その他の諸費用」に大きく分けられます。まずはどのような部分で出費が発生するのかを押さえておきましょう。
ここからは、3種類の費用内訳の概要について解説します。
土地代
注文住宅を建てるとき、予算の大きな割合を占めるのが土地代です。
都市部や利便性の高い場所に家を建てる場合は、土地代を高めに見積もる必要があります。すでに土地を所有していればコストはかかりませんが、家を建てるための土地改良に費用がかかることもあるので注意が必要です。
「フラット35利用者調査」によると、土地付き注文住宅の費用は建設費が全国平均約3405万円、土地取得費が約1497万円で、その比率は約7:3です。
これは、建物そのものの費用が土地の費用よりも高くなる傾向を示しています。建築会社の中には全体的なスケジュールや資金計画の相談に乗ってくれるところもあるため、土地選びの前に建築会社を決めるのも良い方法です。そうすることで、土地と建物のトータルバランスを考慮した計画が立てやすくなります。
参照:住宅金融支援機構 2023年度フラット35利用者調査
建築費
建築費には、基礎工事や内装・外装工事など、家を建てるうえで必要な工事の費用がすべて含まれます。
一般的に、ハウスメーカーに依頼すると費用が高く、工務店に依頼すると安くなります。これは、大手ハウスメーカーは広告やモデルハウスの維持に多額のコストをかけているためです。集客を図るための費用が建築費にも上乗せされるので、地域密着型の工務店よりもコストが高くなります。
工務店に依頼すれば、同じレベルの設備の住宅が大手ハウスメーカーより3割ほど安く建てられるといわれています。ただし、工務店に依頼するときは、信用できる業者かどうかをしっかりと確かめることが大切です。
その他の諸費用
住宅購入時には、工事費用以外に不動産取得税、登録免許税、仲介手数料、住宅ローン手数料、火災保険料、表示登記費用、印紙代などの税金や手数料がかかります。
これらの諸費用は、土地代と建築費の合計額の10〜12%程度を見込むのが一般的です。特に住宅ローンを利用する場合は、印紙税やローン保証料、団体信用生命保険料なども加わるため、全体の予算に大きな影響を与えます。そのため、事前の十分な計画と準備がとても重要です。

注文住宅の費用相場

注文住宅の費用相場は、すでに土地を保有している「土地あり」の場合と、これから土地を購入する「土地なし」の場合で大きく異なります。ここでは、住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」を基に、それぞれの全国平均について解説します。ご自身の状況に合わせて、費用感を把握する参考にしてください。
土地あり
住宅金融支援機構の調査によると、すでに土地を持っている方が注文住宅を建てる場合の全国平均費用は約3,863万円です。前年の約3,717万円と比較して146万円ほど高くなっており、建物の建築費用が近年急激に上昇していることが分かります。これは資材価格の高騰などが背景にあるとされます。
土地を保有しているため、購入費用がかからず、資金のほとんどを建築費に充てられる点が大きなメリットです。
理想の住まいづくりに費用をかけやすくなりますが、注意すべき点もあります。既存の土地でも地盤が弱い場合は、安全確保のために地盤改良工事が必要になることがあり、これには追加費用が発生します。そのため、事前に土地の状態を確認し、予算に組み込んでおくことが重要です。
参照:住宅金融支援機構 2023年度フラット35利用者調査
土地なし
土地をこれから購入して注文住宅を建てる場合の全国平均費用は、約4,903万円です。これは前年の約4,694万円より209万円増えており、土地価格も上昇傾向にあることを示しています。
土地購入費単体の平均額は約1,500万円。住宅取得の資金に占める土地の割合は高いため、建物自体にかかる費用とのバランスを考慮し、慎重に資金計画を立てることが重要です。
参照:住宅金融支援機構 2023年度フラット35利用者調査

地域別の注文住宅の費用相場
注文住宅の費用は、地域によって大きく異なります。特に首都圏や近畿圏は、土地の有無にかかわらず全国平均を上回る傾向にあります。これは、建築需要や人口が多い都市部ほど、建築費や地価が高くなるためです。
以下の表は、各エリアの費用相場を示しています(住宅金融支援機構「2023年フラット35利用者調査」より)。
| エリア | 保有の土地がある場合 | 保有の土地がない場合 | 土地購入費 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3,863万円 | 4,903万円 | 1,498万円 |
| 首都圏 | 4,195万円 | 5,680万円 | 2,277万円 |
| 近畿圏 | 4,142万円 | 5,265万円 | 1,851万円 |
| 東海圏 | 3,897万円 | 4,811万円 | 1,319万円 |
| その他地域 | 3,625万円 | 4,299万円 | 915万円 |
ただし、地価がそれほど高くないエリアでも、地盤改良工事などが必要な場合は費用が高額になる可能性があるので注意しましょう。

20坪・30坪・40坪の注文住宅の費用相場
「2023年度フラット35利用者調査」によると、注文住宅の坪単価は全国平均で約107万円です。これを基準にすると、20坪の家は約2,140万円、30坪では約3,210万円、40坪では約4,280万円が費用の目安となります。
しかし、これらの金額はあくまで平均であり、実際には建築面積や間取り、設備のグレード、依頼する住宅会社によって価格は大きく変動します。建物の費用だけでなく、土地代や外構工事費用なども総予算に含めて計画することが大切です。

頭金に合わせた資金計画の立て方

住宅購入予算を決めるには、まず用意できる頭金を考えます。通常、頭金は住宅購入額の20%以上、少なくても10%は用意したほうがいいと言われています。そこで、現在の貯蓄額から入居するための引越し費用、仮住まい費用などを引いて、いくら頭金にまわせるか計算してみてください。
もし、頭金1,000万円(住宅購入額の20%)用意できるようなら、4,000万円までの住宅を購入できる計算になります。ただし、年収や完済までの期間を考えると、一概に4,000万円までの住宅ローンを組めるとは言い切れません。
それでは、住宅ローンの観点から資金計画を考えてみましょう。住宅ローンの返済はおよそ30年前後と長期間に渡ります。ポイントは定年までに完済できるかどうか。現在35歳で定年が65歳だとしたら、65-35=30で、返済の最長期間は30年を目安にしたいところです。
また、低金利ローンは利息が少なく済むため魅力的ですが、金利変動型や固定期間選択型のケースが多く、景気の動向と関係してくるため注意が必要です。支払い金額をハッキリさせたいのであれば、多少金利が高くても全期間固定型がおすすめ。返済期間と金利に年収を加えて、住宅ローンで融資したい金額を決めると良いでしょう。
こだわりに合わせて建築費予算を決めるポイント
自分がどこにこだわりたいのかを明確にしておけば、建築費予算は決めやすくなります。
とにかく安く家を建てたい場合は、1,000万円台のローコスト住宅を希望するとよいでしょう。また、立地にこだわりたい場合は土地代が高くなるため、建築費をなるべく抑える必要があります。1,000万円台または2,000万円台の住宅にすれば、比較的自由に土地を選べるのではないでしょうか。
内外装にこだわりたいのであれば、建築費に多めの予算を割かなければ希望は実現できません。3,000万円以上の建築費予算を確保し、具体的にどのような設備の家が建てられるのかを検討しましょう。全体の予算がそれほど多くない場合は、立地については妥協して、浮いた土地代を建築費にあてることになります。

建築費用ごとの注文住宅の特徴

建築費用にどれだけの予算を割くかによって、建てられる注文住宅の特徴は変わってきます。建築費用ごとの特徴を理解し、自分の求める家がいくらで建てられるのかを把握しておきましょう。
ここからは、建築費1,000万円台、2,000万円台、3,000万円台の注文住宅の特徴を、実際に建てられた家の実例を交えながら詳しくご紹介します。具体的なイメージを掴む参考にしてください。
1,000万円台
建築費が1,000万円台の場合、コストをカットしたシンプルな住宅を建てることになります。
まず、外壁の表面積を少なくするために、長方形や正方形などの単純な形の建物になるでしょう。屋根については、一方に傾いている片流れ屋根が採用されるのが一般的です。予算オーバーとなるため、基本的に屋上などは設置できません。
また、外壁にもレンガやタイルなどのコストがかかる資材は使えないでしょう。屋内の設備についても、最低限の機能が搭載された安価なものが設置されます。浴室乾燥機など、多機能な設備を採用するのは難しいです。発注した会社に設備が在庫として残っている場合、それを活用することもあります。
構造がシンプルな分、1,000万円台の住宅は完成までの期間が短い傾向にあります。建築は、ローコストでの建築を請け負っている会社に依頼することになるでしょう。
2,000万円台
2,000万円台の注文住宅では、1,000万円台よりも少しグレードアップした資材や設備を使用できます。
希望に応じて、外壁にタイルを使ったり、窓の数を増やしたりすることも可能です。また、浴室やキッチンに最新式の設備を導入できるようになります。ただし、すべての希望を叶えるのは難しいため、優先順位を決めて取り入れていく必要があります。
3,000万円台
建築費3,000万円台の注文住宅では、希望する要素の多くを実現できます。
住宅の形もシンプルな四角形にする必要はなく、敷地を有効活用した形に建てられます。特に、都市部ではいびつな形の土地が多いので、建築費を多めに確保することで敷地を活用できるでしょう。
また、塀や柵を設置したり、床暖房を導入したりすることも可能です。内外装にこだわって高級感のある家にしたいのであれば、3,000万円以上の建築費は必要だと考えておきましょう。

注文住宅を相場より安く予算内で建てるには

注文住宅の費用を抑えるには、仕様や設備のメリハリ、建物の形状をシンプルにするなど、賢い工夫がポイントです。具体的な方法は以下の通りです。
・仕様や設備のグレードにメリハリをつける
・複雑な形状の建物にしない
・水回りをできるだけ集中させる
・壁を少なくする
・湿式工事(左官工事など)を避ける
・造り付け家具を避ける
仕様や設備のグレードにメリハリをつける
使う資材や設備には、安価なものから高価なものまでいろいろあります。なるべく低予算で抑えるには、たとえば壁の仕上げ材はすべてクロスにするとか、お風呂の設備は既製品のシステムバスなどにすることで実現できます。
こだわりたいところとグレードを下げられるところのメリハリをつけることで、資材や設備の費用を抑えましょう。
複雑な形状の建物にしない
住宅は凝った形状よりもシンプルな形のほうが費用は安く済みます。具体的には正方形の建物が安価になります。さらに耐震性もあって安定性が出るというメリットもあります。
水回りをできるだけ集中する
キッチンは1階、洗面台と風呂場は2階など、水回りの設備が離れているとそれだけ配管設備が複雑になり、費用がかかります。水まわり設備は1ヶ所に集中させることで配管工事費の節約になります。
壁を少なくする
部屋数を多くするとそれだけ壁を設置しなければならず、その分だけ費用がかかります。費用を節約したいのであれば、壁を少なくしたほうが良いでしょう。広々とした室内空間が実現でき、採光や通風の面からもおすすめです。
ただし、壁が少ないため耐震補強はしっかり施しましょう。
湿式工事を避ける
湿式工事とは、モルタルや塗料などで壁を仕上げる工事のことです。職人が何度も材料を塗る湿式工事は手間がかかり、その分コストも高くなります。そのため、予算を節約したいのであれば湿式工事は避け、乾式工事で壁を仕上げるとよいでしょう。
外壁にはサイディングを、内装にはクロスをといったように、なるべく乾式工事にすることでコストを抑えられます。
造り付け家具を避ける
造り付け家具とは、住宅の内装に合わせて職人が新たに仕立てる家具のことです。住宅内のスペースを有効活用でき、雰囲気も統一感が出るので造り付け家具は人気があります。
しかし、現場で加工することになるため、コストが高くなりやすいという欠点があります。なるべく造り付け家具は避け、置き家具にすることでコストを抑えられるでしょう。

注文住宅の相場を理解し予算内で理想の住まいを実現しよう
注文住宅の何よりのメリットは、こだわりを自由に表現できることです。しかし、こだわりや憧れを突き詰めていくと、住宅の建築コストはどうしても高くなってしまいます。では、コストが見合わないからこだわりを諦めなければならないのかというと、そうとも限りません。
例えば、表現したいテイストを出すために検討している建材候補は本当にそれだけなのか、実際の暮らしの中で思ったよりも使われないものはないかなど、幅広い候補やご要望の優先度を明確にすることで、本当に欲しかったものが何だったのかが見えてくることもあります。また、設計の工夫によっても、リーズナブルにご要望を実現することも可能です。
フリーダムアーキテクツでは、年間約400棟の注文住宅を手がけています。一棟一棟がすべて異なるご要望から設計され、ひとつとして同じお宅はありません。その中で培ってきた豊富な技術とアイディアから、思わぬ発見が見つかることもありますので、まずは様々な建築実例をご参照してみてください。
> 1,000万円台の建築実例
> 2,000万円台の建築実例
> 3,000万円台の建築実例

注文住宅の費用相場についてよくある質問に回答
注文住宅の費用相場に関するよくある質問に、フリーダムアーキテクツがお答えします。家づくりの疑問をここで解消しましょう。
年収がいくらあれば注文住宅を建てられますか?
国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅を取得した世帯で最も多い年収層は600万円以上800万円未満(22.2%)です。これに400万円以上600万円未満(19.1%)と800万円以上1,000万円未満(17.4%)が続き、400万円以上1,000万円未満の世帯が全体の約半数を占めています。
また、約8割(79.5%)の世帯が住宅ローンを利用しており、年間返済額は平均155.2万円、返済負担率は19.4%です。このデータから、幅広い年収層の方が注文住宅を建てていることがわかります。
年収いくらあれば4000万円のローンを組んでも大丈夫ですか?
一般的に、住宅ローンの借り入れは年収の5〜7倍が適正範囲とされています。この基準に照らすと、4,000万円のローンを組むには少なくとも年収600万円以上が目安です。
ただし、日々の生活費や将来の貯蓄を考慮すると、より安心して返済を続けていくためには年収670万円以上が望ましいといえるでしょう。無理のない返済計画を立てるためにも、年収を基準にした借入可能額の試算が有効です。
35年の住宅ローンは何歳まで組めますか?
住宅ローンは、借り入れ時の年齢だけでなく、完済時の年齢にも上限が設けられています。多くの金融機関では「80歳未満」を完済時年齢の上限としているため、35年ローンを組む場合、借り入れ時の年齢は44歳が上限となります。
なお、住宅金融支援機構の「フラット35」では完済時年齢が80歳なので、35年ローンを組むことのできる上限は45歳です。ローンを組む際は、完済時の年齢も考慮して計画しましょう。
無料住宅作品集の取り寄せ
建築費ごとの実例を含む、約40の実例写真・間取り・価格をご紹介。資料請求いただいた皆様に、無料でお届けします。
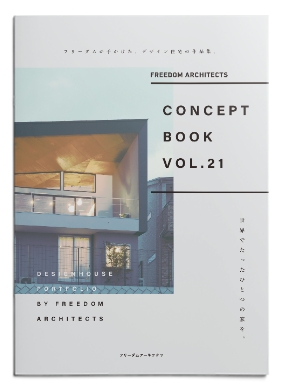
住宅作品集を取り寄せる
注文住宅・デザイナーズハウス
の建築実例を探す
全国で年間約400棟の注文住宅を
設計しているからこそ、事例も豊富

この記事を書いた人

FREEDOM ARCHITECTS
長谷川 稔
1971年生まれの関西出身者。情報出版会社を経て2014年よりFREEDOM株式会社へJoin。現在プロモーション担当としてフリーダムの魅力を伝えています。